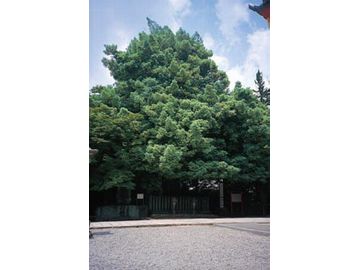武家の棟梁 平氏一族の史跡を訪ねるコース
有田地域
平清盛を中心とする平家一族は、近畿地方を中心に伊勢から瀬戸内海、九州まで多くの足跡を残している。平氏一族は、経済的基盤と軍事的基盤を整えて勢力を伸ばし、後白河法皇と近臣、公卿が企てた鹿ケ谷(ししがたに)の陰謀が発覚した治承元年(1177年)、清盛は即座に公卿や後白河法皇の近臣を処罰し、その2年後には、法皇を捕らえて幽閉している。さらに都を福原へと遷都させている。このような歴史的事象から平氏政権をわが国初の武家政権とみる歴史家が増えている。
平氏一族と紀伊国との関わりは、伝承も含めて幾つか指摘されている。平氏の棟梁であった平忠盛やその子の清盛も院の近習として熊野参詣に同行している。有田市の糸我峠での出来事が文献記録に残されている。『平家物語』の巻第6「祇園女御」には、糸我峠における伝説が記されている。平忠盛は白河院が寵愛していた祇園女御を賜っていたが、その女御は白河院の子を宿していたので、白河院は「生まれる子が女子であれば我が子にし、男子であれば忠盛の子にして武士にせよ」と仰せられた。まもなく男子が産まれ、忠盛はそのことを奏上しようと思っていたが、適当な機会がなかった。白河院が熊野御幸の途中、糸我峠に輿を据えさせてしばらく御休息された。その時、忠盛は藪にぬかご(山芋)がいくつもあったのを見つけてそれを採り、白河院に「いもが子ははふほどにこそなりにけれ」と申し上げた。すると院は直ちに気づき、「ただもり取りてやしなひにせよ」と後の句を付けた。忠盛は山芋にかけて女御が男子を産んだことを報告し、院もすぐに察知して連歌にてこれを詠まれた。この時から忠盛は自分の子として養うようになり、その男子が後の平清盛であるという。